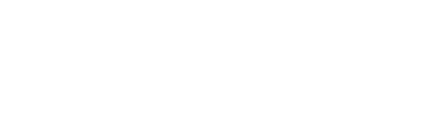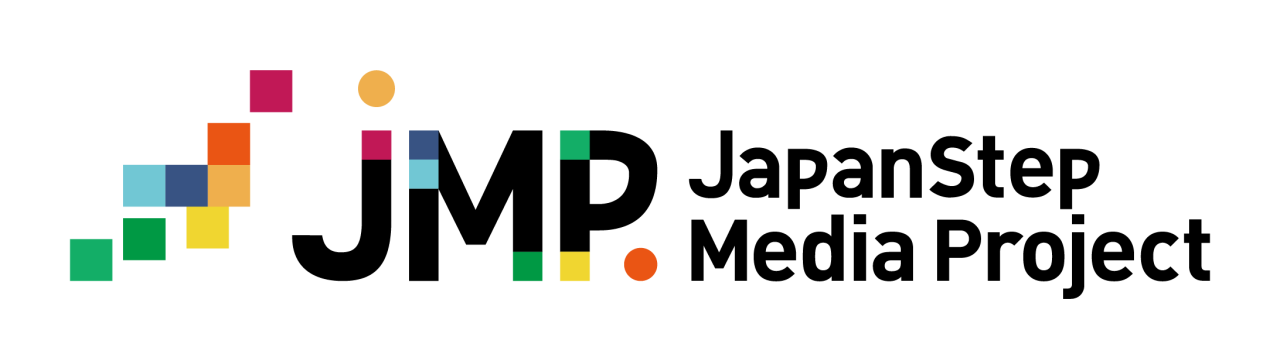- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース

(引用元:PR TIMES)
燃料が尽きれば、ただの宇宙ごみ(デブリ)。人工衛星が抱えるこの宿命を、軌道上で“給油”することで解決する壮大な挑戦が、国の重要プロジェクトとして本格始動する。デブリ除去サービスのパイオニアであるアストロスケールが、科学技術振興機構(JST)から最大108億円規模の研究開発を受注。衛星の寿命を延ばし、宇宙の持続可能性を根底から変えるこの事業は、日本の宇宙開発における新たな一章の幕開けを告げるものだ。
デブリ除去技術を応用 〜実証衛星「REFLEX-J」を打ち上げへ
今回株式会社アストロスケールが受注したのは、内閣府が主導する「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称、K Program)」の一環だ。これは、国の安全保障や経済活動に不可欠な重要技術を育成することを目的とした国家プロジェクトであり、宇宙における燃料補給技術が、いかに戦略的に重要視されているかを示している。
アストロスケールはこの5カ年計画で、宇宙空間における燃料補給技術の実証を行う。その土台となるのが、同社がデブリ除去ミッションで世界に先駆けて実証してきた「RPOD(ランデブ・近傍運用・ドッキング)」技術だ。これは、宇宙空間で対象となる衛星に安全に接近し、ドッキング(結合)するための一連の技術の総称である。この高度な“捕獲技術”にロボットアームや燃料移送の技術を組み合わせることで、協力衛星(燃料補給の対象となる衛星)への燃料補給を実現する。
この実証のために開発される衛星の名称は「REFLEX-J」に決定した。「柔軟性の拡張(Refueling for Extension and Flexibility)」という名が示す通り、この技術は衛星運用のあり方をより柔軟なものへと変革する可能性を秘めている。2029年頃に予定されている軌道上実証が成功すれば、宇宙インフラの新たなスタンダードを築く大きな一歩となるだろう。
「使い捨て」から「循環型」へ。宇宙を持続可能にする新たな経済圏
なぜ今、衛星への燃料補給がこれほど重要視されているのか。アストロスケールの代表取締役社長 加藤 英毅 氏は、その背景にある思想を「循環型経済を宇宙空間で実現することが重要」だと語る。
地球周回軌道は、増加し続ける衛星やデブリによって混雑化が加速しており、このままでは宇宙空間の持続的な利用そのものが困難になりかねない。この危機に対し、加藤氏は「Reduce(削減)、Reuse(再利用)、Repair(修理)、Refuel(燃料補給)、Remove(除去)」という循環型のソリューションが必要不可欠だと説く。これまでデブリの「除去(Remove)」で市場をリードしてきた同社が、デブリを未然に防ぐ「燃料補給(Refuel)」へと事業領域を広げるのは、必然の流れなのだ。
燃料補給サービスが実現すれば、衛星運用者には計り知れないメリットがもたらされる。まず、衛星の寿命を大幅に延長できるため、新たな衛星の製造や打ち上げの回数を減らすことができ、結果的にコスト削減とデブリ発生の抑制に繋がる。さらに、「どうせ燃料が尽きるから」と諦めていた軌道変更や追加ミッションも可能になり、衛星活用の柔軟性が飛躍的に向上する。
アストロスケールは、この燃料補給技術を化学燃料だけでなく、将来主流となる電気推進の燃料補給にも応用することを見据えている。デブリという“過去の負債”をクリーンにする事業から、衛星を“長く大切に使う”未来のインフラを創造する事業へ。アストロスケールの挑戦は、宇宙を「使い捨てのフロンティア」から「持続可能な経済圏」へと変革するための重要な鍵を握っている。