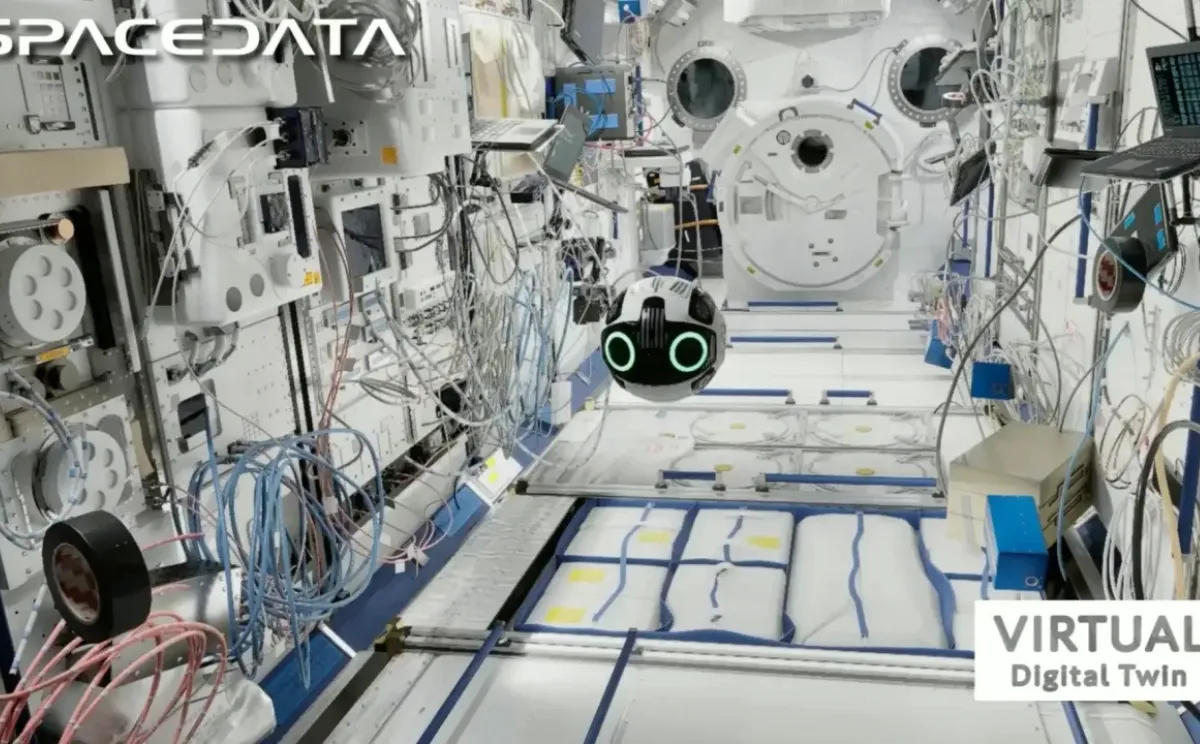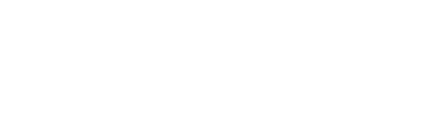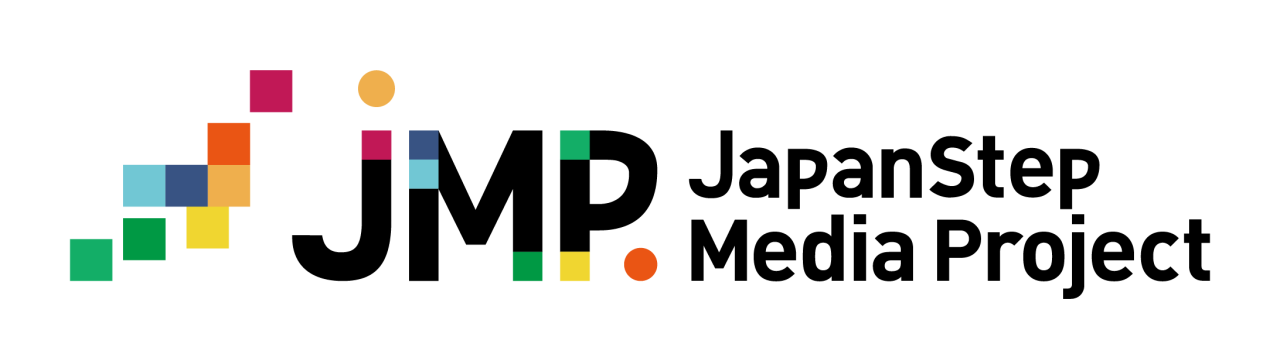- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース

(引用元:PR TIMES)
夏の空を覆い、甚大な被害をもたらす線状降水帯。その発生予測は、現代の気象学における最重要課題の一つだ。この難問に、地上から太陽光などを利用して遠隔で大気の状態を観測する「リモートセンシング」というアプローチで挑む研究が大きな成果を上げた。千葉大学の研究グループが、大気の下層に存在する水蒸気の「濃度のばらつき」こそが豪雨の引き金になることを、6年間の長期観測によって世界で初めて突き止めたのだ。気象庁の最新モデルでも見逃されていたこの“兆候”を捉える新手法は、豪雨災害の早期警戒システムを大きく前進させる可能性を秘めている。
従来の観測網が見逃していた水蒸気の「水平方向の不均一性」
集中豪雨や線状降水帯が発生する際、そのエネルギー源となるのが、地上から約1kmまでの大気下層に流れ込む暖かく湿った空気、すなわち大量の水蒸気だ。この水蒸気の動きをいかに正確に捉えるかが、予測精度を左右する鍵となる。
しかし、従来の観測手法には限界があった。気球を飛ばすラジオゾンデ観測は精度が高いものの、観測地点が全国16カ所と限られている。GPSやマイクロ波放射計は広範囲を観測できるが、高度方向の細かい変化を捉えるのは苦手だ。そのため、特定の地域で水蒸気濃度が局所的にどうなっているか、その「水平方向の不均一性(場所ごとの違い)」を継続的に監視することは極めて困難だった。
この課題に、千葉大学の研究グループは「A-SKY/MAX-DOAS法」という地上設置型のリモートセンシング技術で挑んだ。これは、太陽光が大気を通過する際に特定の気体(今回は水蒸気)に吸収される光のスペクトルを解析する手法だ。研究グループは、千葉大学の屋上に東西南北4方向を向く観測システムを設置。これにより、従来は困難だった特定地点における水蒸気濃度の「方向ごとの違い」を、長期間にわたって高精度に観測することに成功した。さらに、つくばで行われた6年間の観測データを従来のラジオゾンデと比較したところ、相関係数0.971という極めて高い一致を示し、この手法の信頼性の高さも証明された。

(引用元:PR TIMES)
大気の不安定さと連動する“兆候”、数値予報モデルを進化させる新たな視点
6年間にわたる膨大な観測データが明らかにしたのは、衝撃的な事実だった。大気の状態が不安定な時ほど、4方向で観測される水蒸気濃度に顕著な「ばらつき(不均一性)」が現れる傾向があったのだ。特に、水蒸気の不均一性が顕著だった15事例を詳しく分析すると、そのうち10事例は千葉の北側に停滞前線が存在する状況で発生していた。これは、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで、大気の不安定化と水蒸気の不均一性が同時に引き起こされていたことを示唆している。
さらに重要なのは、このA-SKY/MAX-DOAS法で捉えられた水蒸気の不均一性が、気象庁が運用する高解像度の数値予報モデル(局地解析)では適切に検出されていなかったという点だ。これは、現在の最先端の予測モデルでさえも見落としている、豪雨発生前の重要な“兆候”が存在することを示している。この研究を率いた千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 入江 仁士 教授は、この成果が予測精度向上に不可欠であると確信している。
本研究は、A-SKY/MAX-DOAS法が豪雨予測の精度を向上させるための新たな武器となり得ることを科学的に証明した。今後は、この観測網をさらに拡充し、他の観測手法と組み合わせることで、より広域かつ高精度な水蒸気構造の把握を目指すという。地上から空を見上げるこの地道な観測こそが、未来の天気予報を書き換え、私たちの命と暮らしを守るための重要な一歩となるに違いない。